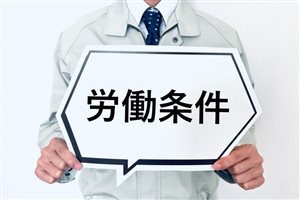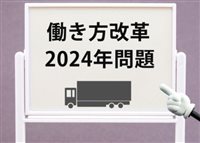貨物軽自動車登録基準貨物運送事業法に基く届出なので、法の要件を満たす必要があります。営業所営業活動及び運転者の管理を行う拠点であり、自宅に営業所を設置することもできます。自動車車庫原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は、営業所から2㎞以内に確保。全ての車両が容易に収容できる広さを有し、他の用途に使用する部分と明確な区分が必要。使用権原を有、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要。一般貨物と同じで住居地域や市街化調整区域等は一般貨物と同じで要件が厳しいのは同じです。休憩施設乗務員が有効に利用することができる適切な施設を確保。自宅に休憩施設を設置することも可能。事業用自動車事業を行うための適切な構造であること。二輪の自動車については、総排気量125㏄を超えるものについて届出が必要。原付、原付2種、免許でいえば原付免許、原付、小型限定の場合は届出不要です。運送約款国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成。「標準約款」と同一のものを設定することも可能。管理体制過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保。アルコール検知器は必要、車両が10台以上で整備管理者の選任が必要になります。運賃・料金荷主に対して不当とならないように設定。特定の荷主が決まっている場合は、荷主と相談して定めることも可能。軽乗用車の登録緩和貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」において、「届出に係る軽自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規定されています。一方、「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされました。貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところですが、今般、「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定します。なお、軽乗用車を使用する場合であっても、使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要です。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
「 軽貨物 」の検索結果
-
-
貨物軽の登録後遵守事項軽貨物自動車運送事業者に対しても、関係法令において以下に示すような安全確保等. にかかる規定があります。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
-
貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の比較項目貨物軽自動車運送事業一般貨物自動車運送事業事業開始届出制許可制運行管理運行管理者の選任義務なし義務あり事故の報告義務なし義務あり運行記録計による記録義務なし義務あり乗務等の記録義務なし義務あり適性診断の受診、初任運転者等に対する特別な指導義務なし義務あり点呼義務あり従業員に対する指導及び監督義務あり運転者が遵守すべき事項酒気を帯びて乗務しないこと等遵守義務あり運転者の勤務時間等の遵守義務あり異常気象時における措置義務あり点検整備義務あり監査監査対象法改正の検討中です。フリーランス・事業者間取引適正化等法令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が可決成立し、同年5月12日に公布されました。同法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
-
個人事業者等の健康管理に関するガイドライン厚生労働省HP個人事業者等の業務上の災害防止を図るため、災害の実態把握や、災害防止のための安全衛生対策について検討した、厚生労働省の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」(座長:土橋 律 東京大学大学院工業系研究科教授)の報告書(令和5年10月)で提言された個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、個人事業者等が健康に就業にするために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す目的で、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を別添のとおり策定しました。個人事業者等の健康管理に関するガイドライン都道府県労働局長あて通知文リーフレット(「「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました」)
-
趣旨我が国における働き⽅の多様化の進展に鑑み、個⼈が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国⺠経済の健全な発展に寄与することを⽬的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明⽰を義務付ける等の措置を講ずる。対象者概要1.対象となる当事者・取引の定義(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相⼿⽅である事業者であって従業員を使⽤しないものをいう。(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個⼈及び特定受託事業者である法⼈の代表者をいう。(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成⼜は役務の提供を委託することをいう。(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使⽤するものをいう。※ 「従業員」には、短時間・短期間等の⼀時的に雇⽤される者は含まない。2.特定受託事業者に係る取引の適正化(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書⾯⼜は電磁的⽅法により明⽰しなければならないものとする。※従業員を使⽤していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を⾏うときについても同様とする。(2)特定受託事業者の給付を受領した⽇から60⽇以内の報酬⽀払期⽇を設定し、⽀払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から⽀払いを受ける期⽇から30⽇以内)(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の⾏為をしてはならないものとし、⑥・⑦の⾏為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を⾏うこと④ 通常相場に⽐べ著しく低い報酬の額を不当に定めること⑤ 正当な理由なく⾃⼰の指定する物の購⼊・役務の利⽤を強制すること⑥ ⾃⼰のために⾦銭、役務その他の経済上の利益を提供させること⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、⼜はやり直させること3.特定受託業務従事者の就業環境の整備(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表⽰等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。(2)特定受託事業者が育児介護等と両⽴して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業務委託」)に係る業務を⾏えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント⾏為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除⽇等の30⽇前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。4.罰則規定違反した場合等の対応公正取引委員会、中⼩企業庁⻑官⼜は厚⽣労働⼤⾂は、特定業務委託事業者等に対し、違反⾏為について助⾔、指導、報告徴収・⽴⼊検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰⾦に処する。法⼈両罰規定あり。5.国が⾏う相談対応等の取組国が⾏う相談対応等の取組国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)リーフレット中小企業庁HP
-
参考:貨物軽自動車安全管理者の選任等(2月13日時点)第三十六条の二 貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。一 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者二 前号に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、第三項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前二年以内に修了した者三 当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者2 貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。3 貨物軽自動車運送事業者は、第一項の貨物軽自動車安全管理者(第十六条第一項の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く。)に、その選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第五十八条の十六第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。一般貨物自動車運送事業との比較項目貨物軽自動車運送事業一般貨物自動車運送事業事業開始届出制許可制運行管理運行管理者の選任義務なし(改正)義務あり事故の報告義務なし(改正)義務あり運行記録計による記録義務なし義務あり乗務等の記録義務なし(改正)義務あり適性診断の受診、初任運転者等に対する特別な指導義務なし(改正)義務あり点呼義務あり従業員に対する指導及び監督義務あり運転者が遵守すべき事項酒気を帯びて乗務しないこと等遵守義務あり運転者の勤務時間等の遵守義務あり異常気象時における措置義務あり点検整備義務あり監査監査対象
-
例えばこんなお悩みを解決するサポートを致します。運送業を初め物流業界は変革期を迎えています。これまでの様々な規制緩和により許可は取得しやすい状況になりました。許可要件を揃えさえすれば申請し許可を受けることは出来ます。しかし、許可を受けてから事業を存続させるためには従来以上にコンプライアンスが求められています。また、事業を発展させる過程では様々な許認可も必要になるでしょう。幣所は、運送業・物流業に特化した事務所です。運送業の行政手続きに止まらずその後に必要となる許認可取得から予防法務、運営に関するコンサルティングなど幅広い領域でサポートしております。新規参入、業務拡大したいが許認可の取得方法が分からない営業所の移転、車庫の新設をしたい営業区域を拡大し他県でも業務をしたい事業用トラックを増車、減車したい事業報告など書類作成がわずらわしい巡回指導が来るが何を準備したら、、、Gマーク取得したい関連する許可が必要になった貨物自動車運送事業の許可有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説をお知りになりたい方はこちらのページにお進みください。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。貨物軽自動車運送事業届出軽自動車で運送業を始めるときは、軽貨物自動車運送経営許可の届出が必要となります。運送業の許可取得後のサポート運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検など運送業の適正運営をサポートしております。運送業許可後の認可・届出運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得後の事業計画変更の認可、各種届出について詳しく解説しています。運送業関連の認定制度愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業者が取得すべきGマーク、働きやすい職場認定制度などサポートしております。産業廃棄物収集運搬業の許可運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可や自動車の登録に関することも幣所に相談下さい。関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。産業廃棄物収集運搬業愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。産業廃棄物を収集し運搬するときは、産業は器物収集運搬業の許可が必要です。古物商の許可愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。古物の売買をするときは古物商の許可が必要です。自動車の登録関係自動車の名義変更愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。売買や相続で車の所有者の変更があったときは、名義変更の手続きが必要になります。また、管轄登録事務所が変更になったときはナンバープレートの変更も必要です。車庫証明代行愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。自動車を購入する時など駐車する車庫の車庫証明が必要になります。※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。倉庫業を始めるには倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法の営業倉庫の登録について倉庫業登録の種類、申請方法、配置しなければならない倉庫管理主任者を詳しく解説しています。土地利用関係運送業・倉庫業の許認可には土地利用関係が多く関わります。幣所は許可に伴う農地転用、都市計画法の許可も実績があります。土地利用関係愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。営業所の測量、図面作成全く図面のない運送業の営業所や車庫でも大丈夫です。許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。報酬愛知県の行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。各業務の目安報酬を掲示しております。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。お問合せ電話 090-1280-1331FAX 0568-55-5884〒481-0039 住所 愛知県北名古屋市法成寺松の木36番地GFAいけやま行政書士事務所#ui-datepicker-div{z-index:10000 !important;}.ui-datepicker-calendar th,.ui-datepicker-calendar td{min-width:unset !important;}select.ui-datepicker-year,select.ui-datepicker-month{height:2em !important;gap:5px;}span.del + span.del{display:none !important;}お問い合わせフォーム内容の確認以下の内容で送信します。よろしいですか?氏名必須メールアドレス必須お問い合わせ内容必須お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。